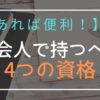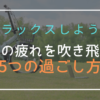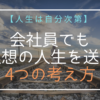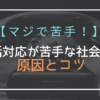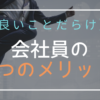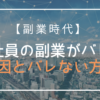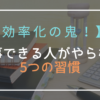退職後にやっておくべき6つの手順【退職後のチェックリスト】
「ついに退職することができた!」と思って一旦仕事をことは忘れてのんびりするのもいいですが、退職後はやらなければならないことがいくつかあります。
退職をした翌日から新しい会社で働く場合には、特に気にする必要はありません。
しかし退職後に転職活動を始めようと思っている方は、いくつかやるべきことがあります。
そこで今回は「退職後にやっておくべき6つの手順」を紹介していきます。
実際に僕が新卒で入った会社を退職した際にやっていたことをまとめたので参考になるかと思います。
それでは早速内容にいきましょう。
退職後にやっておくべき6つの手順

まず結論からです。ここでは退職後にやっておくべきことを順番通りにまとめてみました。
もし「退職後に何をしたらいいか分からない」という方はこちらを参考にしてみてください。
①スーツをクリーニングに出す
退職後すぐに働かない人の場合は、使っていたスーツ全てをクリーニングに出すようにしましょう。
普段働いている状態だと、なかなか忙しくてクリーニングに出すのもめんどくさいと感じることも多いです。
ですが退職後であれば、スーツを着る機会はしばらく訪れないのでこれを機にクリーニングに出しちゃいましょう。
他にも革靴をキレイに手入れしたり、使っていたビジネスリュックやバッグを整理したりするのもいいでしょう。
毎日の仕事で忙しくておろそかにしてしまった細かい部分をここではやっていきましょう。
②退職した会社から書類等を受け取る
会社を退職するといくつか書類を受け取ることになるはずです。
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者証
- 離職票
- 退職証明書
などですね。
書類によっては失業手当の申請だったり、国民健康保険への切り替えの手続きで必要になったりするので必ず受け取るようにしましょう。
僕の場合「年金手帳」と「雇用保険被保険者証」は退職日に受け取り、「退職証明書」と「離職票」は後日郵送されました。
もしかすると会社側の漏れや、連携ミスによって書類の郵送が遅れたり、そもそも発送を忘れてしまわれる可能性があります。
その場合には会社にきちんと問い合わせをしましょう。「退職証明書」と「離職票」がないと色んな手当が受けられなくなるので、自分自身が損をすることになっちゃいます。
③国民健康保険への切り替え
会社を退職すると、健康保険の資格を喪失してしまいます。健康保険の資格が使えなくなるということは、病院での診察代が10割負担になるのでできるだけ早めに手続きをするようにしましょう。
期限としては退職してから14日以内に手続きを行う必要があります。必要な書類は身分証明書と退職証明書又は離職票があればOKです。
そもそも国民健康保険って?
国民健康保険とは「会社員や公務員以外の人を対象にした社会保険」のことを言います。
つまり会社員でない人や自営業やフリーランスの人が入る保険ということです。
この国民健康保険のお金は、自分で納付する必要があるので注意しましょう。
また会社員時代に入っていた社会保険との違いはあまりありません。
しかし
- 子供を産んだ時にもらえる出産手当金
- 病気やケガで仕事ができる状態でない時にもらえる傷病手当金
は国民健康保険では貰うことができません。
そこが大きな違いです。
健康保険と聞くとほとんどの人が恩恵を受けるのが「医療費の3割負担」だと思います。
医療費の3割負担は、国民健康保険でも適用されるのでその点は安心してください。
会社員時代に入っていた保険は「健康保険」
会社員でいる時に加入していた保険を「健康保険」と言います。
給料から毎月引かれているので、保険料を払っていた感覚がないと思いますがしっかりと払っていたものです。
医療費の3割負担はもちろん、出産手当金や傷病手当金などを貰うことができるので手厚い健康保険と言えます。
④国民年金への切り替え
国民年金は20歳以上の方であれば、必ず払わなければならない義務となっています。
会社員の時は、厚生年金という国民年金とセットになった年金を払っていたので問題ありませんでした。
しかし会社を退職すると厚生年金の天引きがなくなり、自分で払う必要があります。
なのできちんと手続きを行わないと、変なトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるので、これも退職してから14日以内に手続きをするようにしましょう。
国民年金と厚生年金の違いって?
会社員時代には「厚生年金」という年金を給料から天引きされる形で支払っていました。
厚生年金とは「厚生年金+国民年金」といったイメージを持っていただければOKです。
国民年金は国民の義務で支払う必要があるので、あなたの給料から天引きされます。
では残りの厚生年金の部分は誰が払うのでしょうか?それは会社です。
会社側は国民年金でかかった費用の同額を厚生年金として上乗せしてまとめて支払う仕組みになっています。
例えば毎月の国民年金が16,590円(令和4年時点)だとします。
すると会社側は国民年金と同額を支払う必要があるので16,590円を用意します。
つまり「16,590+16,590」で合計33,180円の厚生年金が納付されるのです。
ざっくり言うと、社員は16,590円の年金を負担するだけで、実質33,180円の年金を納付したことになるのです。
これが厚生年金です。
ここではざっくりとした紹介なので、気になる方は⬇︎のサイトを見ることをおすすめします。
厚生年金とは何かをわかりやすく解説|いくらもらえる?いつまで払う?
⑤失業手当の申請
会社を退職したことを証明する「離職票」は、退職してから10日後を目安に自宅に届くようになっています。
離職票が自宅に届いたら、あなたの住んでいる地域のハローワークにいって失業手当の申請をしにいきましょう。
失業手当の申請が早ければ早いほど、手当を受けられる期間が早くなるのでおすすめです。
とりあえずここでは「離職票が届いたらすぐにハローワークに行く」ことを覚えておけばOKです。
⑥住民税の支払い
会社員でいる時は、住民税は自動的に天引きされる仕組みとなっていました。
しかし会社を退職すると住民税は自分で納付する必要があります。
ほとんどの場合、住民税の支払いを書類によって各市役所から届くようになっています。
住民税の支払いが遅れてしまうと、脱税とみなされ最悪の場合さらに税がプラスされて返ってくることもあるので早めに手続きをするようにしましょう。
また退職した月によっては、残った住民税の分を最後の給料から一気に天引きされるケースもあります。
その場合は特に自分から住民税の支払いの手続きをする必要はありません。
住民税ってなに?
住民税とは地方税の一種で、都道府県が課税する道府県民税(東京都は都民税)と、市区町村が課税する市町村民税(区市町村民税)の総称です。教育、福祉、救急、ゴミ処理など、地方自治体が提供する公共サービスをまかなうために使われます。
まとめ:退職後に迷ったらこの記事を参考に
退職した後にやるべきことを手順にまとめると
- スーツをクリーニングに出す
- 退職した会社から書類等を受け取る
- 国民健康保険への切り替え
- 国民年金への切り替え
- 失業手当の申請
- 住民税の支払い
です。
意外とやることがあって大変そうに思えますが、少しずつ着実にやっていけば特に問題ないので難しく思う必要はありません。
手続きについても市役所やハローワークにいけば、担当の人が丁寧に説明してくれるので気軽にいきましょう。
ということで今回は「退職後にやっておくべき6つの手順」についてお話ししました。